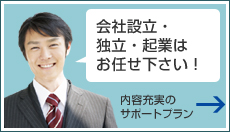お役立ち情報
これからの法改正の動きこれからの法改正の動き
兵庫県知事をめぐる内部告発に関する問題などにより、公益通報者をいかに守るかについての議論が活発になっています。
昨年末、消費者庁が設けた有識者による「公益通報者保護制度検討会」が報告書を公表しました。
報告書では、公益通報者の保護や事業者の体制整備とその実効性に関し、引き続き課題が多く、国民の安心・安全を脅かすような不正の発生を防止し、我が国の企業が海外進出や投資などで悪影響を受けることがないよう、可能な限り早期に課題に対処し、制度の高度化を図る必要があるとしています。
具体的には、
(1)事業者における体制整備義務の履行の徹底や、実効性の向上を図ること
(2)労働者等による公益通報を阻害する要因に適切に対処すること
(3)公益通報を理由とする不利益な取扱いを抑止し、救済措置を強化すること
(4)公益通報の実施状況や不利益な取扱いの実態にあわせて、通報主体の範囲を拡大すること
等が考えられるとしています。
そして公益通報者保護制度が実効的に機能し、不正が早期に発見・是正され、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護が確実に図られるようにすべきであるとしています。
この報告書を受け、政府がまとめた公益通報者保護法改正案の骨子について、自民党は大筋で了承しました。骨子にまとめられた改正の概要は次のとおりです。
・ 公益通報を理由に解雇や懲戒処分を行なった事業者等に対して、刑事罰を導入
・ 事業者に対しては3000万円以下の罰金、個人に対しては6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す
・ 通報に対処する従事者の指定義務を怠った事業者に対して、国が立入検査をできる権限を創設する。是正命令に従わない場合などに対しては刑事罰を導入
・ 通報者を特定する行為を原則禁止する
政府はこの骨子をもとに改正法案を作成し、今期通常国会での改正を目指しています。
注目したい法改正の動向
- マンション老朽化問題対策
-
老朽化したマンションの増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、マンションその他の区分所有建物の建替えや改修を促進して管理・再生の円滑化等を図るため、国土交通省は区分所有法の改正案を通常国会に提出する予定です。
区分所有建物の再生等の円滑化を図るため、集会の決議要件の合理化、所有者不明専有部分管理命令(仮称)制度の創設、敷地共有者等集会制度の対象範囲の拡大、マンション管理適正化支援法人(仮称)の登録制度の創設などが、その内容とされています。 - 海運業の人手不足に対応
-
国土交通省は、海運業の人手不足解消に向けて、海上労働の安全・衛生を確保するための教育訓練の義務づけ、地方公共団体による無料の船員職員紹介事業の創設等の措置等の実現を目的に、船員法の改正を目指しています。
あわせて、漁船員の訓練・資格証明等の基準に関する国際条約の的確な実施を確保するため、特定漁船の船員の要件等を定めるとしています。 - 空の安全の確保
-
国土交通省は、航空機の安全を確保することを目的とする航空法の改正案を通常国会に提出する予定です。
内容は、航空機を着陸・離陸させる操縦を行なう者に対する技能発揮訓練の義務づけや、滑走路の誤進入を防止するための施設に関する事項の空港等の機能に関する基準への追加等の措置を講ずるとともに、地方管理空港に係る滑走路等の応急の災害復旧工事の国土交通大臣による代行制度の創設等の措置を講ずること等とされています。 - 再審制の見直し
- 袴田事件の再審無罪確定などを契機に再審制度のあり方が問われています。その見直しに向けて、鈴木馨祐法務大臣は、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会での協議とは別に、法制審議会に諮問し、法整備について検討することを明らかにしました。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック